県内企業の取組等

・自分で働く時間帯や日数を決定でき、随時変更も可能
・子どもスタッフ(子連れ出勤)では宿題や遊びだけでなく、職員の手伝いもすることで、社会勉強にもなっている
導入の経緯・経営者の思い
2009年に職員が主体的に自分たちの働きやすい職場づくりのための取組を検討する「両立支援委員会」を立ち上げました。以降、両立支援委員会が中心となり、その時その時の世情、子どもの成長に合わせた取組を提案し、オリジナルの両立支援制度をつくってきました。両立支援委員会から発信された取組は、不具合があれば修正するなど、柔軟に変化させながら継続しています。子育て支援の制度づくりをきっかけに、地域の中の高寿園として、多様な人の多様な働き方、多様な価値観を大切にする職場風土の醸成を目指しています。
取組内容
ライフステージによって変遷する多様な価値観を大切にする働き方の実現を目指して、「自分の『ハタラク』は自分でつくる」をキャッチコピーとして、以下の取組を実施しています。
(1)自分で選べる勤務形態(選択可能な働き方)
(2)小学校を卒業するまでの短時間正職員制度
(3)子どもスタッフ(子連れ出勤)
(4)介護リフト、ICT機器を活用した業務全般の標準化・効率化の推進
(5)テレワークの導入
(6)育休等復職支援プログラム
(7)育休中の帰園日(育休中の職場とのコミュニケーション)
(8)マイ助産師(妊娠から満1歳まで、法人負担で自分専属の助産師 の助言が受けられる)
(9)おもちゃ図書館の開館(無償の遊び場、おもちゃや絵本の貸し出し)
(10)地域の子育て支援団体との共催事業 月5~6回開催
(11)小中学生の夏休み課題応援と学習支援
(12)子育てママや元気シニア等地域の多様な「ハタラク」の実現

子ども出勤 行事の手伝い

子ども出勤 畑の手伝い

両立支援委員会

取組の効果
子育てしやすい職場環境は、他の職員のゆとりにもなっていて、子どもスタッフとのふれあいも癒しとなっています。働く側も子どもの成長に合わせた働き方が選択できるので喜ばれています。子どもを育てながら働く職員も職場に感謝してくれて、働き続けてもらえることは職場の人材確保、育成の面からもとても有効です。また子どもにとっても社会勉強になりあいさつやマナーを学ぶ機会となっています。お年寄りとの交流は人に親切にする心を育んでいます。
今後取り組みたいこと
子どもが親の仕事を見たり、福祉の体験を行う「子ども参観日」もしくは職員の子ども以外も参加できる「福祉体験ツアー」の企画。令和6年度は、くるみんの申請も準備中です。
カテゴリ
関連事例
ファジアーノ岡山の団体観戦と小学生対象イベントへの協賛・参加 ~100万円の使いみち~
会社名:セリオ株式会社
業種 :情報通信業
子ども参観日 ~100万円の使いみち~第2弾
会社名:有限会社三協鋲螺
業種 :卸売・小売業
社風を支えてくれる社員に賞与として還元 ~100万円の使いみち~
会社名:株式会社行雲
業種 :飲食サービス業
子育て応援金を支給 ~100万円の使いみち~
会社名:有限会社三協鋲螺
業種 :卸売・小売業
子どもも楽しめるフェスティバル ~100万円の使いみち~
会社名:医療法人自由会
業種 :医療業
奨励金+αを全従業員に分配 ~100万円の使いみち~
会社名:ナガオ株式会社
業種 :製造業
【受賞区分】製造業(令和6年度)
会社名:株式会社フジワラテクノアート
業種 :製造業
【受賞区分】卸売業、小売業(令和6年度)
会社名:有限会社三協鋲螺(さんきょうびょうら)
業種 :卸売・小売業





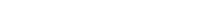
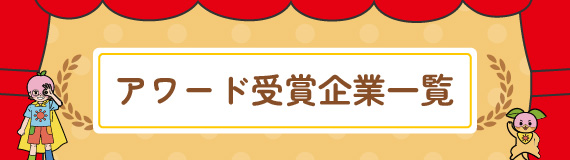
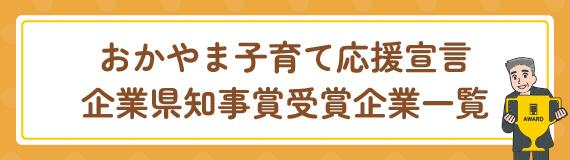
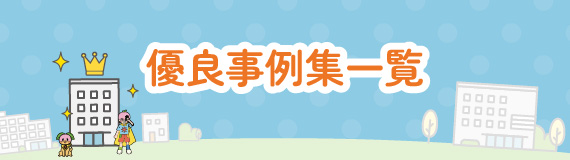
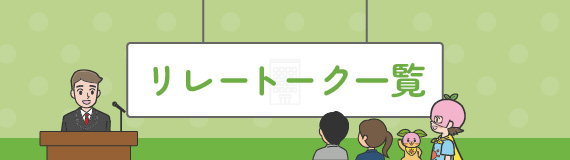
審査員コメント
・53通りの豊富な勤務パターンから、自分で勤務形態を選ぶことができ、また、随時変更もでき、自由な働き方を実現している。
・子どもスタッフ(子連れ出勤)は長期休暇などに子どもと一緒に出勤でき、また職員の手伝いもさせてくれ、子どもにとっても社会勉強になる。